2025年シーズン前半戦、FC東京は何度も降格圏に突入するという厳しいシーズンを送っている。

6/20日、小原GM自身が一昨年解任したアルベル監督を更に下回る成績を出している松橋監督について続投を明言した。
FC東京・小原GM、松橋監督の続投を明言 積極補強で後半戦の巻き返しに自信(スポニチアネックス) – Yahoo!ニュース
ここで名言されている続投のロジックは攻撃と守備で大きくまとめるとこうだ
- (攻撃面について)ビッグチャンスの数はリーグでも5番以内でありビッグチャンスは作れているが決めきれなかった。加えて攻撃陣に怪我が多かった
- (守備について)攻撃で言えば、後ろに人数が重たくなってしまって前に人数を掛けきれなかった。システムに限らず、失点はリーグでワーストなので。だから、3バックが全てではない
攻撃の人数かけられていないという割にはビッグチャンスを作れていて決めきれてなかっただけといっておりやや一貫性に欠ける印象がある。
加えて、多くの方が違和感を抱いたのは「ビッグチャンスの数」という概念ではないだろうか。ここで川岸社長による昨年度の総括を振り返りたい。
ゴール期待値を簡単に表現すると、どれだけゴールを決めるチャンスがあったかということです。色々な算出方法があるようですが、データスタジアムによれば、FC東京のゴール期待値は1.21でした。それに対して1試合平均で1.39得点という数字が出ているので、効率良く点をとっていたと言えます。少ないチャンスで決め切ったケースが多かったわけです。期待値はシュートの回数や打った場所などの組み合わせから算出していくのですが、その値が低いということは確率が低いシュートが多かったことになります。結局、ゴールは増えたものの、ゴール前まで行けていないとか、チャンスが少なかった印象を抱かせたのかなと。
長いシーズンやシーズンを繰り返すごとに、ゴール期待値とゴール数は、だいたい近い数字になることはよく言われています。今シーズンは昨シーズン対比でゴール数は増えたので効率良く得点がとれて良かったのですが、これは毎シーズン再現できるものではないとも思っています。
ゴール期待値はあくまで結果指標なので参考データではありますが、しかしながら重要な要素の一つです。前任のピーター クラモフスキー前監督、その前のアルベル プッチ オルトネダ元監督もJ2リーグ時代に残していた数値は非常に良く、ゴール率が高くて被ゴール率が低かったですが、そこにはカテゴリーや所属選手の違いもあり、監督だけに起因するものではないにせよ、FC東京でそのまま再現できなかった。
上記からわかるのは、
- データスタジアム(Jリーグにデータを提供及び自社でFootball labを運営)のデータである「ゴール期待値」を重視しており、監督選びにも用いている
- 長いシーズンや複数年において、ゴール期待値とゴール数は近接すると考えている
ここで改めて続投基準と、昨シーズン総括を見比べると、利用している数字がゴール期待値からビッグチャンスを逃した数に代わっていることが確認出来る(ちなみにゴール期待値は去年同様今年も冴えないどころか6/20時点では昨年比で悪化している)。また、J公式やフットボールラボにはビッグチャンスを逃した数というスタッツはない。
ではビッグチャンスを逃した数はどこからきているのか?これはFC東京が契約しているデータサイトのものだろう。各社指標は異なるが、無料で見られる指標にFotMob社の数字がある。ここできになるのは、確かに今シーズンビッグチャンスを逃した数を逃した数は多いが、それは昨年もである、という事実(今年2位、昨年6位)である
ビッグチャンスを逃した回数 – 2025のJ. Leagueスタッツ
小原GMが用いたスタッツがどの会社の数字をベースにしたかは不明瞭なものの、ビッグチャンスを逃した数という指標では恐らくゴール期待値が2年続けてマイナスであり、少なくともFotMob社のデータでは昨年も高いことから、昨シーズンも高かったと想定されるため、クラモフスキー解任・松橋続投という結論は出所が異なる統計数字を用いてあとから正当化しているだけで合理的な一貫性があるようにはみえないと言わざる負えない。
小原GMのコメントは不明瞭であり、また引用される統計数字も毎度異なり都合がよく自身を擁護するための数字を毎回持ってきている印象があり誠実さに欠けるだけでなく自信がない印象を周りに余計に与えて自分で首を絞めているのではないか
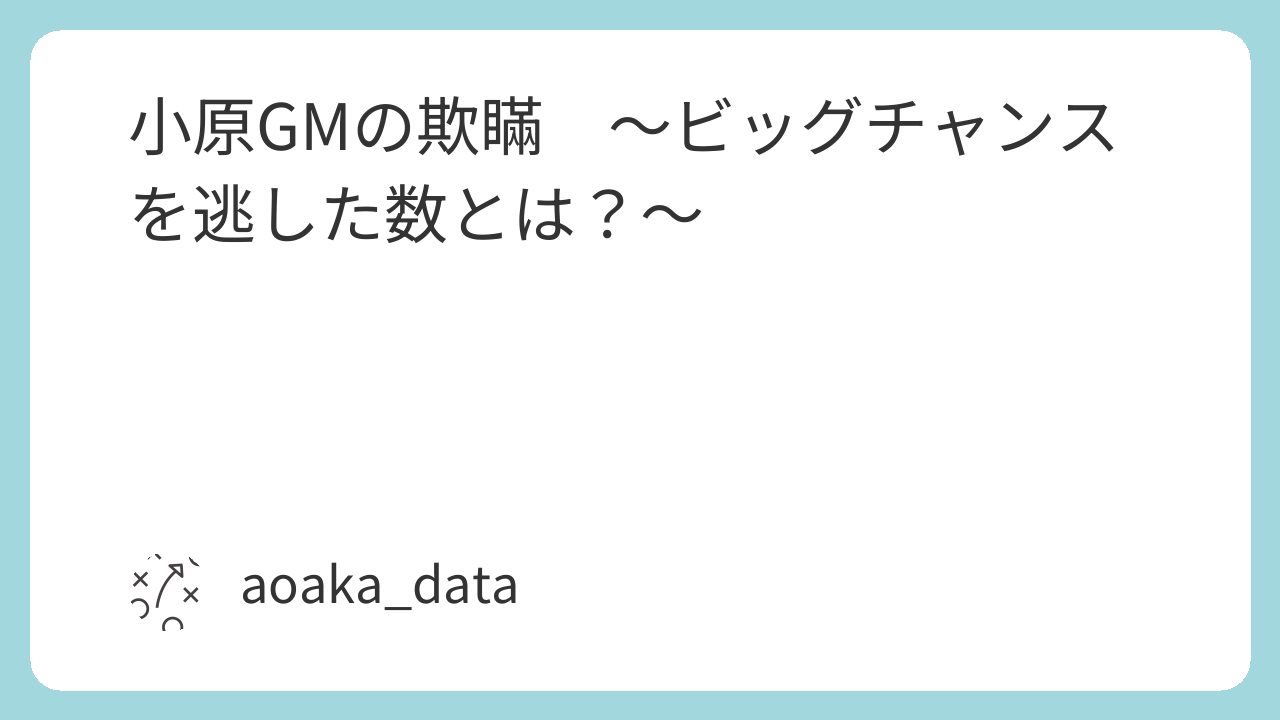
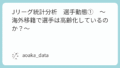
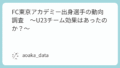
コメント